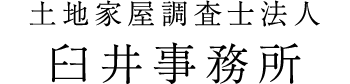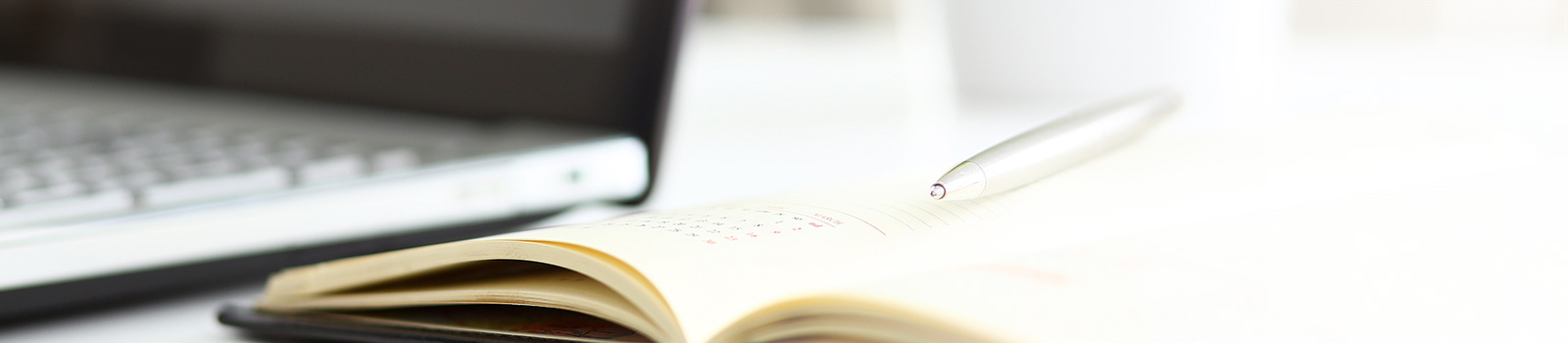自宅の増築・リフォーム!知らずに放置しがちな「登記」の落とし穴

自宅の増築や大規模なリフォームは、マイホームの価値を高め、生活をより豊かにする素晴らしい一大行事です。しかし、間取りや設備の検討に熱中するあまり、「登記」という重要な手続きがおろそかになりがちです。
増築・リフォームで建物の構造や床面積に変更があった場合、法務局への届出が義務付けられており、これを怠ると将来的に大きな「落とし穴」に直面する危険性があるのです。
そこで本記事では、土地家屋調査士の視点から、増改築時の登記の必要性と、放置した場合のリスクについて詳しく解説いたします。
目次
1.増築・リフォームで「登記」のことは考えていますか?
自宅の改修工事が無事に完了し、新しくなった空間での生活に心が躍る瞬間は格別でしょう。しかし、その喜びの裏側で、建物の実態と公的な記録との間に「ズレ」が生じてしまっている可能性を、認識しておく必要があります。
このズレは、将来的に思わぬトラブルの火種となりかねません。大切な資産を守るためにも、工事後の手続きについてしっかりと考えていきましょう。
1)そのリフォーム・増築は「登記」の変更が必要かも
一般的に、増築というと床面積が増えるケースを想像されるでしょう。例えば、リビングにサンルームを増設したり、使っていなかったベランダを室内化したりといった工事です。
また、内装の変更だけにとどまらず、二世帯住宅化に伴い出入口を新設したり、建物の用途を変更したりする工事も、法務局に備え付けられた公的な記録を変更する必要が生じる可能性が高いです。建物の物理的な状況に変更が生じた際には、必ず登記の必要性を確認しなければなりません。
2)土地家屋調査士が教える「登記の落とし穴」とは
建物の登記記録は、いわばマイホームの「公的な履歴書」です。この履歴書が現状と一致しない場合、将来、建物を売却したり、相続が発生したりした際に、各種手続きが滞ってしまうという「落とし穴」が存在します。
増築から何十年も経ってから、慌てて登記しようとしても、当時の図面や資料が残っておらず、手続きが非常に困難になるケースも少なくありません。登記は「義務」であり、放置すること自体が大きなリスクとなるのです。

2.「なぜ?」を解消!増築・リフォームで必要な登記とは
増築やリフォームの際に「登記が必要」と言われても、「なぜそんな手続きがいるのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。この手続きは、建物の実態を公的に証明し、権利関係の安全性を確保することにあります。特に、金融機関が担保として評価したり、固定資産税の計算の基礎となったりする重要な情報のため、正確性が求められるのです。
1)増築登記(建物表題部変更登記)とは?
増築や一部取り壊しなどで建物の物理的な状況に変更が生じた際に申請する登記を、増築登記(建物表題部変更登記)と呼びます。表題部とは、登記簿の中で建物の所在地、種類、構造、床面積などを記録している部分を指します。この登記は、建物の所有者に申請する義務があり、変更が発生した日から1カ月以内に行わなければなりません。
2)どんな変更で登記が必要になる?具体例でチェック
登記が必要となる変更は、床面積の増減だけにとどまりません。具体的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
| 床面積の増加 | 部屋やサンルームの増築、ビルトインガレージの居室化など。 |
| 床面積の減少 | 納屋や物置の取り壊し、一部を解体して庭にするなど。 |
| 構造・種類の変更 | 木造から鉄骨造への変更、物置から居宅への用途変更など。 |
| 建物の合体・分割 | 隣接する二棟の建物を一つに繋げる、一棟を二棟に分けるなど。 |
見た目の小さな変更であっても、建物の同一性に影響を与える場合は、登記の専門家である土地家屋調査士に相談することが賢明です。
3)リフォームでも注意!「新築当時の情報」とのズレをなくす重要性
増築を伴わないリフォームであっても、注意が必要です。特に、古い建物の登記簿には、新築当時の測量技術や記載方法が反映されており、実際の建物の位置や形状と微妙にズレていることがあります。
大規模なリフォームを機に、現況に合わせた正確な測量と登記情報の修正(更正登記)を行うことで、将来的な境界トラブルや権利関係の問題を未然に防ぐことができます。登記情報と実態を完全に一致させることこそが、安心につながる重要なポイントです。
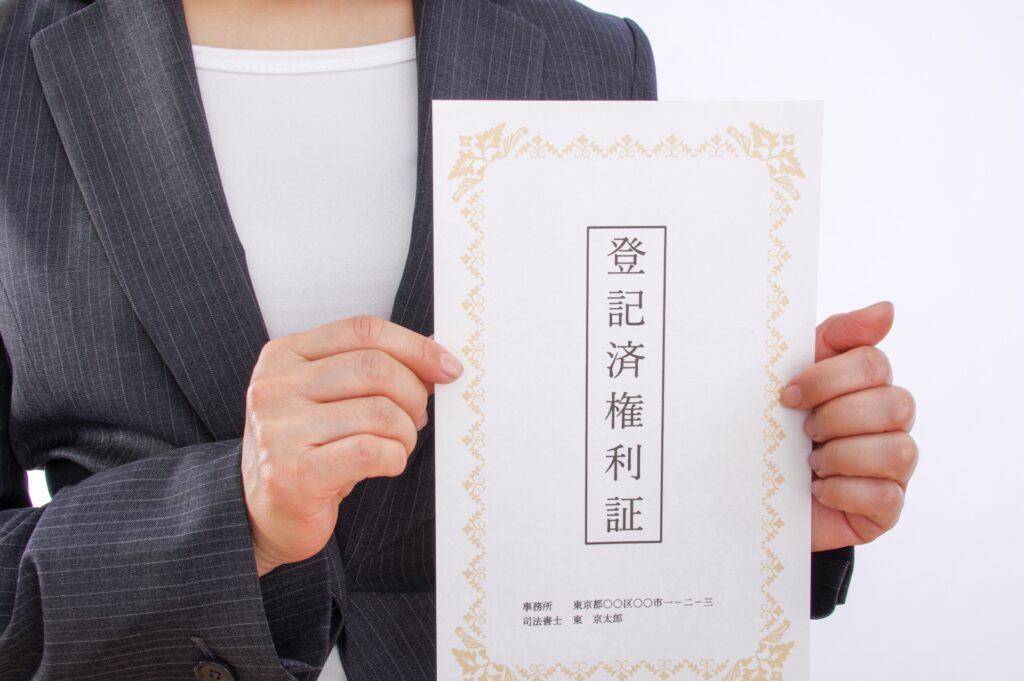
3.放置するとどうなる?未来のあなたを困らせる3大リスク
「忙しいから」「費用がかかるから」といった理由で登記を後回しにすることは、結果として未来の自分や家族に大きな負担を強いることになりかねません。建物の登記変更を怠ることで発生する、特に注意すべき3つの大きなリスクについて解説します。
1)【売却・相続時】スムーズな手続きが不可能に
不動産の売買や相続の際には、法務局の登記情報に基づいて手続きが進められます。しかし、増築部分の登記がない場合、公的な記録上の面積と、実際の建物の面積が一致しません。
買主や相続人は、登記簿に記載されていない部分について所有権を主張できず、取引自体がストップしてしまいます。売却を急いでいるときに、遡って複雑な登記手続きを行う必要が生じ、時間も費用も余計にかかってしまうのです。
2)【ローン・融資】担保評価に関わる大きな問題
自宅を担保に入れて新たなローンを組む際や、借り換えを行う際にも、登記の不備は問題となります。金融機関は、登記簿に記載されている面積や構造に基づいて、その建物の担保価値を評価します。
登記されていない増築部分は、担保評価の対象外となり、希望通りの融資額を得られない可能性があります。また、融資実行の条件として、まず増築登記を完了させることを求められるのが一般的です。
3)【法律】罰則の対象になる可能性も(10万円以下の過料)
建物表題部変更登記は、法律で申請義務が定められています。具体的には、不動産登記法第47条第1項により、変更があった日から1カ月以内の申請が義務付けられています。
この期間内に正当な理由なく申請を怠った場合、同法第164条に基づき10万円以下の過料(罰金)に処される可能性があります。罰則の適用を受ける可能性は低いとはいえ、義務を怠っているという事実は、法令遵守の観点からも望ましくありません。
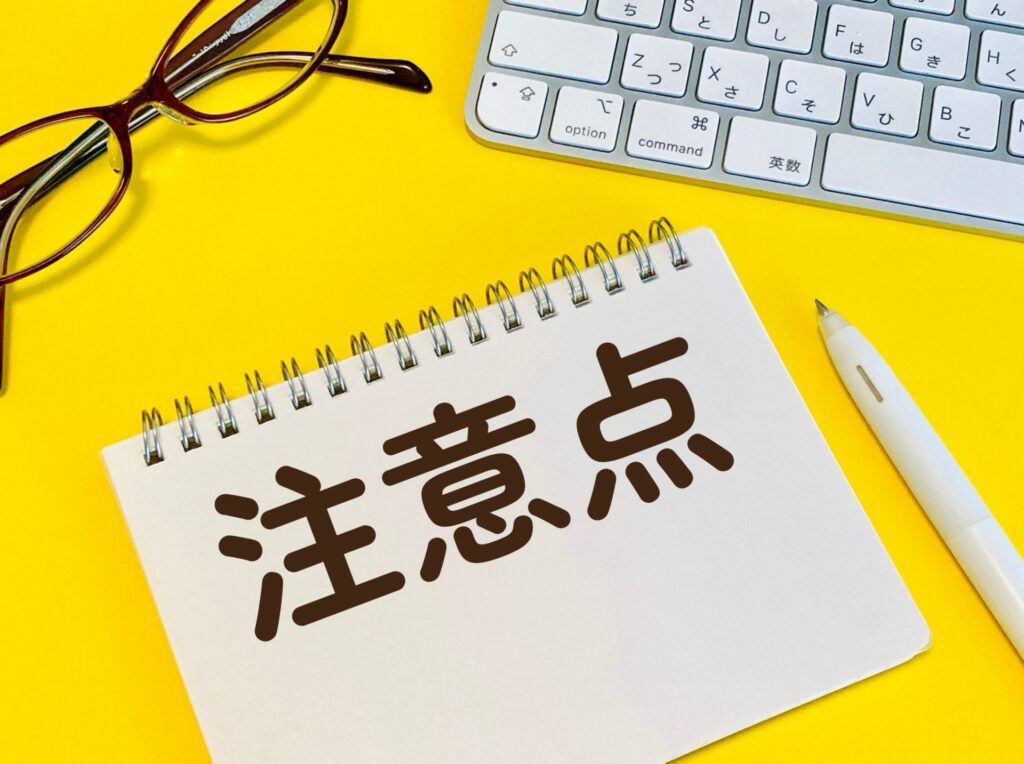
4.まとめ:安心・安全なマイホームのために
知らなかったでは済まされない!登記はマイホームの「身分証明書」
自宅の増築・リフォーム後の登記手続きは、単なる面倒な事務作業ではなく、大切なマイホームの資産価値と、ご家族の権利を守るための「身分証明書」を整える行為にほかなりません。
建物の実態と公的な記録を一致させておくことで、将来的な売買や相続、金融取引をスムーズかつ安全に進めることができるようになります。登記の放置は「未来への負債」であることを、ぜひ心に留めておいてください。
無料相談のススメ:まずは土地家屋調査士法人 臼井事務所にご相談ください
増築登記(建物表題部変更登記)には、建物の正確な測量や専門的な図面作成が不可欠であり、一般の方が自力で行うには非常に手間と知識が必要です。私ども土地家屋調査士法人 臼井事務所は、豊富な経験と専門知識をもって、お客様の登記手続きを迅速かつ正確にサポートいたします。
「うちの増築は登記が必要?」といったご質問から、「何十年も前の増築を今から登記したい」といった複雑なケースまで、まずは無料相談をご利用いただき、不安を解消するところから始めませんか。どうぞお気軽にお問い合わせください。

シェアする