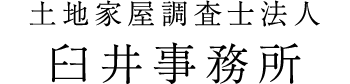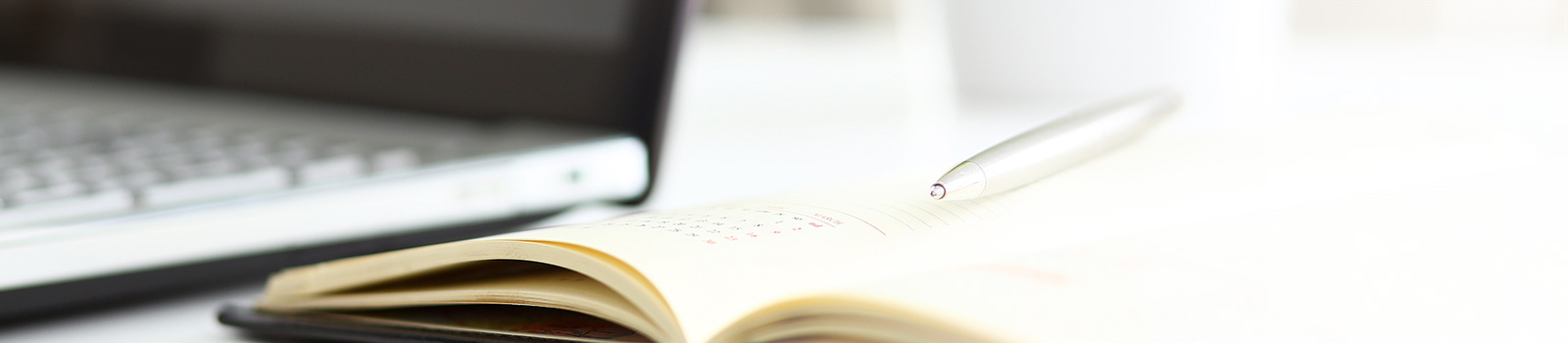【土地購入】測量済み物件は本当に安心?注意すべきポイントと境界確認の落とし穴

土地の購入は人生における大きな決断であり、特にその土地が「測量済み」とされている場合、多くの方が安心感を抱くのではないでしょうか。
しかし、この「測量済み」という言葉の裏には、様々な意味合いやリスクが潜んでいることをご存じでしょうか。一見すると明確に思える土地の状況も、測量の種類やその内容によっては、思わぬ落とし穴が存在することもあります。
そこでこの記事では、土地家屋調査士の視点から「測量済み」物件に潜むリスクや、購入前に必ず確認すべきポイント、そして専門家へ相談することの重要性について詳しく解説します。安心して土地を手に入れるために、ぜひご一読いただければ幸いです。
目次
1.「測量済み」物件とは?安心の裏に潜むリスク
「測量済み」と聞くと、土地の状況が明確で安心だと感じがちですが、その実態は様々です。
1)測量済み物件の定義とメリット
「測量済み」物件とは、その名の通り、すでに測量が行われている土地を指します。一般的に、土地の面積や形状が数値として把握されているため、買主は売買契約時に具体的な情報を得られるというメリットがあります。
これにより、土地の利用計画が立てやすくなり、金融機関も担保評価を行いやすくなるでしょう。しかし、一言で「測量済み」と言っても、測量の目的や方法によってその信頼性は大きく異なるため、注意が必要です。
2)測量方法の種類と信頼性の違い
土地の測量には、主に現況測量と確定測量という二つの種類が存在します。現況測量は、現在の土地の状況を把握することを目的とし、隣接地所有者の立ち会いを伴わないため、境界の確定には至りません。
一方、確定測量は、隣接地所有者全員の立ち会いのもと、公法上の境界を確定させることを目的とする測量で、その結果は法的な拘束力を持ちます。当然ながら、後者の方が土地の境界が明確になり、将来的なトラブルを回避できるため、信頼性は格段に高まります。
3)「測量済み」だけでは安心できない理由
「測量済み」という表示だけで安心してしまうのは危険です。なぜなら、その測量が前述の現況測量であった場合、隣地との境界が確定しているわけではないからです。
もし現況測量図しか存在しない場合、将来的に隣地所有者との間で境界に関する認識の相違が生じ、トラブルに発展する可能性が残ります。測量が行われた時期が古い場合も、当時の測量技術や精度、あるいは現在の土地利用状況の変化などにより、現状と異なるケースも考えられます。

2.測量図の種類と確認すべきポイント
土地の測量図にはいくつか種類があり、それぞれ法的な意味合いや確認すべき項目が異なります。
1)現況測量図と確定測量図の違い
現況測量図は、土地の現況つまり建物や構造物、高低差などを計測し、その状態を記録した図面です。これはあくまで現状の把握を目的としており、隣接地との正確な境界線を確定するものではありません。
一方、確定測量図は、土地の境界を法的に確定させるために作成される図面であり、隣接地所有者との合意に基づいて作成されます。この確定測量図には、境界標の位置や座標、そして隣接所有者の署名・捺印が記載されており、非常に高い信頼性を持っています。
2)確定測量図の重要性と信頼性
土地を購入する際に最も重視すべきは、この確定測量図の有無です。確定測量図があるということは、その土地の境界が明確に確定していることを意味し、将来的な境界トラブルのリスクを大幅に低減できます。
金融機関も確定測量図が存在する物件に対しては、安心して融資を行う傾向があります。売買契約においても、確定測量図を添付することで、買主は安心して土地を取得できるでしょう。
3)古い測量図の注意点
測量図が作成された時期が古い場合は、特に注意が必要です。以前の測量技術は現在ほど精度が高くなかった可能性があり、また、時間の経過とともに道路の拡幅や区画整理など、周囲の状況が変化していることも考えられます。
さらに、古い測量図では、境界標がすでに失われているケースも少なくありません。そのため、測量図が存在しても、それが現状に即しているか、そして境界標が実際に存在し、図面と合致しているかを確認することが重要です。
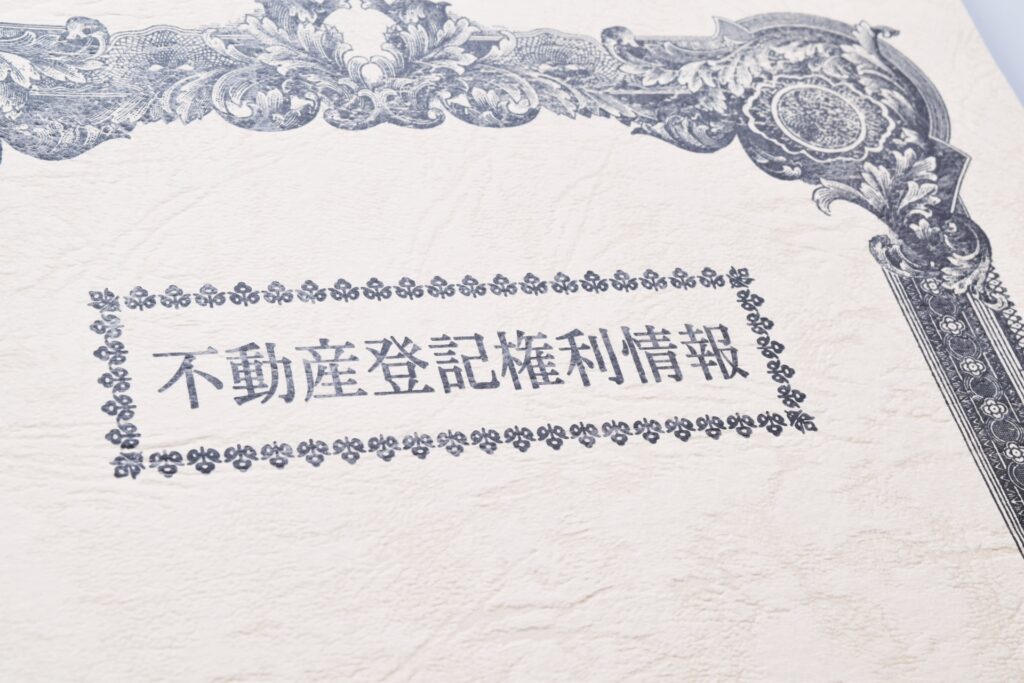
3.境界標の確認と「筆界未定」の落とし穴
土地の境界を示す境界標は非常に重要ですが、設置状況や公的な記録との一致を確認することが不可欠です。
1)境界標の種類と役割
境界標とは、土地と土地の境を示す標識のことで、コンクリート杭、石杭、金属標など、様々な種類があります。これらは土地の物理的な境界を明確にし、隣地との境界に関する認識の相違を防ぐ重要な役割を担っています。境界標は、土地の所有権の範囲を示す目印であり、トラブルを未然に防ぐうえで欠かせない存在です。
2)境界標の確認方法と注意点
土地を購入する際には、現地で実際に境界標が設置されているかを確認することが不可欠です。もし測量図がある場合は、その図面と照らし合わせ、全ての境界標が正しく設置されているか、その位置が図面通りであるかを慎重に確認しましょう。
もし一部の境界標が見当たらない場合や、明らかに移動していると思われる場合は、すぐに売主や仲介業者に確認を求めるべきです。また、境界標の種類によっては、経年劣化により破損している可能性もあるため、注意深く観察することが求められます。
3)境界標がない、または不明確な場合の対処法
もし境界標が全く見当たらない、あるいはその位置が不明確な場合は、「筆界未定」という状態である可能性が高いです。これは、公的な記録上、その土地の境界が確定していないことを意味します。
このような場合、土地を購入すると、将来的に隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じるリスクが高まります。このような状況に直面した際は、安易に購入を進めるのではなく、必ず土地家屋調査士に相談し、確定測量を実施して境界を明確にすることをお勧めします。

4.土地購入前に土地家屋調査士へ相談するメリット
測量済み物件であっても、土地の専門家である土地家屋調査士に事前に相談することで、未然にトラブルを防ぐことができます。
1)土地家屋調査士に相談すべきケース
土地の購入を検討している中で、測量図の種類が不明瞭な場合、測量図が古い場合、現地に境界標が見当たらない場合、あるいは隣地との境界について何らかの懸念がある場合は、迷わず土地家屋調査士に相談すべきです。
将来的に土地を分筆したい、あるいは建物を建築する際に正確な土地の面積を知りたいといった場合も、事前に相談しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
2)専門家がチェックする測量の信頼性
土地家屋調査士は、測量に関する専門的な知識と経験を有しており、既存の測量図が法的に有効なものか、あるいは現在の状況と合致しているかを詳細に確認することができます。
測量図の記載内容や作成された経緯を精査し、その信頼性を客観的に評価してくれるでしょう。これにより、見過ごされがちなリスクを早期に発見し、安心して土地を購入するための判断材料を提供します。
3)境界問題や越境トラブルの未然防止
土地家屋調査士に相談することで、土地の購入前に潜在的な境界問題や越境トラブルを未然に防ぐことが可能です。万が一、境界が不明確な土地であったとしても、確定測量を実施することで、隣地所有者との合意のもと、法的に有効な境界を確定することができます。これにより、購入後に起こり得る隣地との争いを回避し、穏やかな土地利用を実現できるでしょう。
4)将来的なトラブル回避のためのアドバイス
土地家屋調査士は、現在の状況だけでなく、将来的な土地の利用計画や法改正なども考慮に入れ、多角的な視点からアドバイスを提供します。
例えば、将来的な増改築や土地の売却を考えた場合、どのような測量が必要になるか、あるいはどのような点に注意すべきかなど、長期的な視点でのサポートが期待できます。これにより、購入後に予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを、最小限に抑えることができます。
5)土地家屋調査士の選び方と相談の流れ
土地家屋調査士を選ぶ際は、まず実績や専門分野を確認し、ご自身の相談内容に合った事務所を選ぶことが重要です。インターネットでの情報収集や、不動産会社からの紹介なども有効な手段となります。
相談の流れとしては、まず現状の土地に関する情報(物件資料、測量図など)を可能な限り準備し、土地家屋調査士に提示します。その後、具体的な相談内容を伝え、専門家からの見解や提案を聞き、必要であれば測量などの手続きを進めていくことになります。

5.土地の購入の際は「臼井事務所」へご相談ください
土地の購入は、人生で最も大きな買い物の一つです。特に土地の境界は、後々のトラブルに発展しやすいデリケートな問題を含んでいます。「測量済み」という言葉だけで安心せず、専門家である土地家屋調査士のアドバイスも参考に、しっかりとした確認を行うことが、安心して土地を手に入れるための鍵となります。
| ご不明な点やご不安な点がございましたら、いつでもお気軽に「土地家屋調査士法人 臼井事務所」へご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つ私たちが、お客様の土地購入を全力でサポートさせていただきます。安心して土地を取得し、快適な生活を送るためのお手伝いをさせていただければ幸いです。 |

シェアする